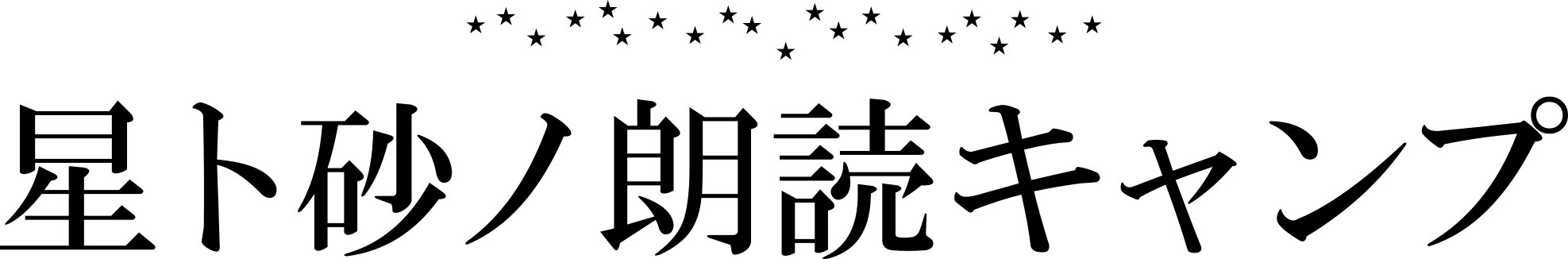VRChat朗読の著作権について
「文ノ旅朗読団」及び「趣味の朗読会」(この2メディアを以下「当メディア」称す)は、バーチャルSNSサービスVRChat上における主催朗読イベントの著作権について、下記の立場を取ります。
記
VRChat朗読の著作権について
WORLDインスタンスにおける、営利を目的としない上演で、かつ30名程度の公衆に当たらないリスナー人数であれば「公衆送信権」の適用は免れ、著作権法に違反しない。
以上
なおこれは判例、文化庁見解によるものではなく、あくまで当メディアの見解であることを注記しておきます。
判断の根拠
上記の立場を取るに至った根拠を明記しておきます。
(判断の根拠1)著作権法に違反しない「朗読」とは
著作権法(営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
(判断の根拠2)仮想空間における著作物利用の政府の見解(2024年6月1日現在)
検討事項2.メタバース上の著作物利用等に係る権利処理
課題2-1;メタバース上のイベント等における著作物のライセンス利用
◎ イベント等をはじめとしたメタバース空間内の様々な活動では、音楽、映像、写真、キャラクターなどの著作物が数多く用いられることが想定されるが、その利用の際には、公衆送信権等との関係など、原則として許諾(ライセンス)を得る必要がある
出典:首相官邸 資料4{現実空間と仮想空間を交錯する知財利用、仮想オブジェクトのデザイン等に関する権利の取扱いについて(討議用メモ)」
※(判断の根拠1)より「原則」から外れる余地があると考える
(判断の根拠3)自動公衆送信とは
公衆の要求に応じて自動的に送信する場合(例:インターネットのホームページ)有線によるもの無線によるものいずれも含む
出典:知的財産用語辞典
(判断の根拠4)関連する法律 著作権法 第23条【公衆送信権等】
1項 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
2項 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
(判断の根拠5)「公衆」とは特定多数を含む
公衆送信権とはどのようなものか
「公衆」とは:(不特定多数・少数に加えて)特定かつ多数の者を含むとされています。マンションの住人のみに配信するような場合でも「公衆」にあたります。
(集合住宅での録画サービスについて: 知財高裁 平成19年6月14日平17(ネ)3258)
※WORLDインスタンスにおける聴き手はFriendオンリー、Friendプラスのいずれにおいても「Friend」が条件であり「特定」に分類することが可能である
(判断の根拠6)なぜ特定多数なのか
著作権法2条5項には、「公衆」には、特定かつ多数の者を含む、と規定されていますが、特定多数の者まで「公衆」に含めるのは、「会員のみが対象なので、不特定の人向けではない」という脱法行為を防ぐためです。(参照:「著作権テキスト~初めて学ぶ人のために~ 平成25年度 / 文化庁長官官房著作権課」)
(判断の根拠7)多数とはどれほどの人数か
法律に規定されているわけではありませんが、文化庁は、一般には「50人を超えれば多数」と考えているようです。(もちろんケースに応じて異なってくるでしょうが。)
出典:弁理士法人ブランシェ国際知的財産事務所―著作権法上の「公衆」:「多数」とはどのくらいの人数?―
当メディアの思い
日本人の読書離れとそれに伴う書店減少がニュースとして取り上げられています。
書店減少はAmazonなどの大手ネット通販の台頭あるいは電子書籍化もその要因でしょう。しかし私たちの生活環境においてすでに書店があまりに少ないというのも事実です。紙の本を手に入れる手段として大手ネット通販の役割は大きいと言わざるを得ません
また諸原料の高騰等から新刊本の価格自体が手を出しにくい方へとどんどん遠ざかっているのも事実。書籍の電子化もまた時代のニーズといえます。
そんななか当メディアはせめて読書の喜びを広めることで読書離れに竿を差すことはできないかと活動しています。
そして読書の喜びは、朗読によって何倍にも拡大できることをみなさんに知っていただきたいと思っています。
当メディアは朗読会に聴き手として参加してくださった方におもしろい本、知らなかった本を紹介することを目的の一つにおいています。
またそれ以上に自分で声に出して物語を読んでみることのメリット―登場人物への感情移入や展開する場面への没入感が格段に違う―を伝える場でもあるのです。朗読を特別な才能を持つ者だけの特技と捉える方が少なくありません。しかし、決してそんなことはなく、朗読は誰にでもできる読書をもっとたのしむための手段なのです。
作者が亡くなり70年以上経過した著作権切れの作品をVRChatで読むのもよいことです。でも当メディアはいまホットな作品も朗読していくことで「ほら、いまのあなたにぴったりなこんな作品もありますよ」と伝えることで読書の喜びを発見していってもらえればと考えています。
みんな本を読んでみませんか。声に出して読んでみませんか。もしかしたらパラレルワールドに生きるあなたがそこにいるかもしれません。それはきっとあなたの精神の血肉となるはずです。